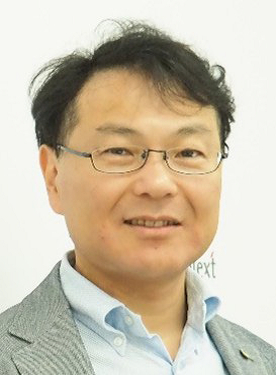
ご挨拶 -経営工学が期待される時代に-
第38期会長 船木謙一
2025 年 6 月 1 日の通常総会で日本経営工学会第 38 期会長を拝命いたしました.多くの皆様からご支援をいただいたことに感謝しますとともに,今後の学会運営におきましては皆様のご協力をお願い申し上げます.
私は大学で経営工学を学び,修士課程ではプラントエンジニアリングを専門に研究しました.その後,株式会社日立製作所に生産システムの研究者として入社し,製造ライン設計,設備管理・保全,生産管理,サプライチェーンマネジメントの研究やシステム開発の他,サービスデザイン,業務プロセス改革などに携わりました.また,研究開発やイノベーション創生のマネジメントとして,大学,研究機関との共同研究の推進に携わり,現在は,コーポレートベンチャーによるスタートアップへの投資やスタートアップとの協業の促進など,オープンイノベーションの戦略と実行に注力しています.スタートアップの社外取締役やベンチャーキャピタルのアドバイザーなどの立場で経営や投資への助言などもしています.日本経営工学会では,各種委員の他,前期は副会長として運営に携わらせていただきました.
日本経営工学会が産業界から会長を迎えるのは 44 年前の第 17 期以来とのことです.第 17 期の会長はトヨタ生産方式で世界的に有名な大野耐一先生であり,それ以来となると大変恐れ多く,気が引き締まる思いです.歴代の諸先輩方が築かれた伝統ある本学会の歩みを振り返ると,改めて責任の重さを感じており,産業界から会長を迎える意義は何か,追求して参ります.私は,経営工学がかつてないほど多面的に必要とされている時代になってきたと肌で感じており,そこに私の役割があると考えます.
今,社会・産業を取り巻く環境の変化に経営が直面する課題は多岐に渡っています.労働力,資源,エネルギー,食料などあらゆるものが不足する中,いかに効率よく持続的な成長を実現できるかが課題になると同時に,気候変動,災害,地経(政)学など,さまざまなリスクにいかに対応するかも問われています.経済の発展による人々の価値観の進化や多様化は,モノからコト,所有からシェアなど価値提供形態の変化と,地域や文化による違いへの対応も迫っています.昨今の AI の進化やバイオサイエンス/エンジニアリングの進歩,新エネルギー開発の挑戦など,科学の進歩と最新技術の普及は,経営が直面する上記の諸課題を解決する強力な武器になる一方,それらをマネジメントの視点から活かし,課題を解決する最適な方法,システムを仕立て上げる経営工学がますます求められます.
翻って,産業界に身を置く私の周辺を見ると,上記のような諸課題の解決に経営工学の知見を活かそうという声を聴くことはあまりありません.そもそも経営工学の存在が認知されていないということもあるようです.これは経営工学の責任学会として由々しき問題ですが,同時に社会・産業全体にとっても大きな損失だと思います.この現状を打開するためには,社会・産業界におけるプレゼンスを高める努力が必要です.私は,産業界から就く会長としてこの問題に全面的に取り組みます.
経営工学のプレゼンスを高めるには,経営工学が社会・産業の課題に向き合い,提供できる価値を示すことが必須です.しかし,前記のように現代の課題は多岐に渡ります.したがって,これまでに取り組んできた課題に加え,新しい課題にも対象を拡げ,研究テーマを果敢に発掘していくことが必要です.たとえば,資源やエネルギーが不足する時代になり,一次,二次,三次を問わず,あらゆる産業においてバイオプロセスの導入が増えていますが,バイオプロセスを含む工程設計,生産管理,品質管理,物流管理,原価管理には多くの課題があります.また,熟練者不足の問題は,製造・物流現場に限らず,あらゆる部門で起こりつつあり,需給調整や部品調達など部門間調整が必要な業務や,サービスの提供やマネジメント業務に AI エージェント(自律的な業務代行 AI)活用を検討する動きがあります.そこでは学習と調整および最適化を繰り返す新しい計画・管理ロジックや新しい IE のあり方が求められるでしょう.社会・産業が直面する新たな課題に応える経営工学を示せれば,プレゼンスも高まると思います.
また,研究のアプローチも多様化しないといけないかもしれません.複雑で多岐に渡る課題に対応するには,システムを要素分解して問題を解くアプローチ(アナリシス)だけでなく,局所と全体の相互作用を理解し,総合して最適なシステムを組み上げるアプローチ(シンセシス)もますます重要になるでしょう.たとえば,これまでは製造コストや生産性を扱う問題は,エネルギー効率や環境負荷と切り離して捉えることができたかもしれませんが,現代の工場運営では製造などの付加価値を生む本業に加えて,廃熱処理や資材循環,電力調達管理(売電,買電,蓄電),水やガスなどのユーティリティ管理を総合的に扱い,最適化することが求められます.サプライチェーンまでマネジメント対象を広げると,さらに複雑な相互作用の考慮が必要になります.まさにシンセシスアプローチです.
以上のような時代において,研究者が果たす役割は,見つけた問題や提示された問題を解くという解決志向だけで満足せず,社会・産業の変化を先読みして新たな問題を提起し,世の中を先導する提言志向の活動を強化しても良いかもしれません.かつて 10 年以上前に,日本経営工学会も企画に協力,一部執筆し,日本技術士会経営工学部会が主導してまとめ上げた「経営工学 2050 ビジョン」やその後の「補遺版」のような素晴らしいアセットもあります.
そして,経営工学の挑戦や成果を社会・産業界にお伝えし,産官学の交流を促進する施策も重要です.あるいはそもそも経営工学の存在を知っていただくために,産官のリーダーの皆様に加えて,学校や予備校など教育界への周知,普及が必要かもしれません.産官学をつなぐ媒体である経営システム誌や,大会,支部活動,研究部門活動を通じた学会内外の知の交流と人脈形成の場は学会が提供できる強力な基盤です.経営工学が期待される時代に,これらの基盤をどう拡充,アップデートしていけば良いか,理事会メンバーと会員の皆様の知恵を集めて検討していきたいと思います.SNS やメタバースなど,デジタル媒体の選択肢も増えている中,新しい研究紹介,人材交流のあり方も工夫の余地があると思います.
第38期の理事会は,上記のような問題意識を共有し,力を合わせて取り組んでいただける素晴らしいリーダーで構成されています.会員の皆様のご協力も得て,時代にふさわしい日本経営工学会の姿を描ければ,長年の悩みである会員数の減少,論文や研究発表の量的,質的拡大,国際化など,学会が抱える問題も良い方向に向かい,活力ある学会へと進化していけると信じています.
会員の皆様のお力添えをいただけますと幸いです.どうぞよろしくお願いいたします.
